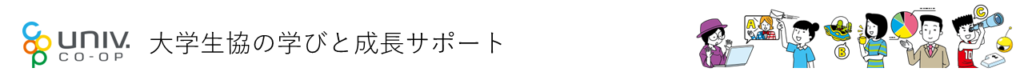First Year Program in KYOTO 2025のChallenge Program 2(CP2)受け入れ先募集要項のページです。京都で大学生活をはじめる新入生が社会との接点を持っていきいきと活動する経験ができるよう、ぜひご検討をお願いいたします。
大学生協体験型講座「First Year Program in Kyoto 2025
チャレンジプログラム−2 受け入れのお願い
2025年4月
大学生協事業連合 学び支援事業部
FYP京都事務局
1.体験講座「First Year Program in Kyoto 2025」の概要
(1)本事業の趣旨
①京都の大学の新入生に、学び体験する場を提供し生活力・人間力を身につけてもらう。
②新入生に大学を超えた仲間づくり、社会(人)とのネットワークづくりの場を提供する。
③社会的課題実践を通して地域・文化・産業・人と交流し、京都の良さを実感してもらう。
④講座を通して大学生活への自信を持ち、4年間の目標・ビジョンを持つきっかけにしてもらう。
(2)参加生協
・京都工芸繊維大学生活協同組合
・京都府立医科大学府立大学生活協同組合(京都府立大学)
・同志社生活協同組合(同志社大学、同志社女子大学)
・京都橘学園生活協同組合(京都橘大学)
・立命館生活協同組合(立命館大学)
・龍谷大学生活協同組合
・京都教育大学 7生協8大学
(3)プログラム概要
①講座名称 First Year Program in Kyoto 2025
②実施期間・コマ数 2025年4月~12月 の間に、14コマを実施
③受講者数 約 名・サポーター (計約 名)
④プログラムの内容 Webサイトをご参照ください。
※講座内の社会的課題実践としてチャレンジプログラムを取り組みます。
2、チャレンジプログラム-2の実施要領
(1)チャレンジプログラムー2の実施概要
①期間 2025年7月12日(土)〜11月15日(土)の間
②場所 受け入れ先企業・団体の事務所・現場など
③参加 受講生(1回生)3〜5名+サポータ(上回生)1〜2名
④課題 協力企業・団体様より提示されたミッションに取り組む
例:商品開発、知名度アップのための広報提案、○○普及の企画開催など
3、実施イメージ、大まかな流れ
(1)事前準備
①事前打ち合わせ
※事務局と担当学生が訪問又はオンラインにて進め方の打ち合わせをさせていただきます。
・チャレンジの進め方の説明、連絡先・方法の確認
・企業様から提示していただく課題についての協議・確認
②受講生への受入先情報提供とチーム編成
・6月7日第5回講座にて受入先の概要と予定されている課題のアウトライン説明
・7月5日第7回講座にてプログラムの詳細説明と希望に基づくチーム編成
(2)顔合わせ、実行計画づくり
①顔合わせ
※7月12日(土)または指定の平日午後等に顔合わせを行います。(オンライン可)
・会社の概要説明〜業務内容、特色、企業理念、規模など
・学生メンバー紹介
・ミッションの提示〜企業様から取り組むべき(解決したい)課題を出していただく
例:製品の広報、製品サービスへの評価レポートなど
②現場見学・ジョブシャドウイング
※7月中旬〜9月中旬の間で企業・団体様と当該チームにて日程を調整していただきます。
・工場、店舗、施設の見学と必要な場合業務体験
・現場での業務内容に関する研修
・ジョブシャドウイング (社員の方の仕事を観察させていただきます)
⑤実行計画の作成
・与えられたミッションの達成に向け、取り組みの内容、スケジュール等を決めます。
・8月、9月のオンライン講座において、プログラムに関する研修を実施します。
・チームで計画作りを行い、講座内で実行計画発表します。(9月20日)
(3)チャレンジ実践とプレゼンテーション・企画実施
①課題解決・実行
・企業・団体内でのアクション 例:企画会議等への参加、実習など
・受入先様への報告・連絡・相談、中間発表な
・会社外へのアプローチ、リサーチ 例:展示会、販売店でのアンケートなど
・仮説—実行—ふりかえり
②企業・団体内での発表とフィードバック
・学生の発表の場を企業・団体内で設定してください。
できるだけ10月下旬〜11月中旬で設定していただくようお願いします。
・学生側のまとめ・レポート発表 〜社長様、ご担当者様宛
・企業・団体様からのフィードバック
(4)成果報告
※11月15日第12回講座で、取り組み結果やふりかえりについて発表
・学生 講座内での結果報告(何をして、何を学べたのか)
・受け入れ企業・団体様よりのコメント
(5)主要スケジュール
〜5月20日 受入先企業・団体の確定
〜6月中旬 事務局およびサポーターによる事前打ち合わせ
7月5日 コース発表とチーム編成、第1回チーム会議
7月12日 顔合わせ、企業・団体様よりミッションの提示
7〜9月 職場・活動見学・ジョブシャドウイング・情報収集、および実行計画づくり
9〜11月 チャレンジ実施と振り返り・まとめ作成、企業・団体様での発表会
11月15日 講座内で取り組み全体のまとめ、実施報告
4、受け入れ企業・団体の募集要領
(1)募集企業・団体数
15〜17組織
(2)応募方法、期限
下記の連絡先まで電子メールにてお申し込みください。なお、都合により下記の期限までにご返信ください。
期限:5月20日(火)
受け入れに当たっての確認事項や進め方について、あらためて打ち合わせさせていただきます。
企画の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
<問い合わせ・連絡先>
First Year Program in KYOTO 事務局 赤木一成
電話 090−8395−6405
Mail fyp-akagi@jobsupport.jp
◆◆◆受け入れのご検討にあたって◆◆◆
(1)インターンシップとのちがい
・本プログラムは、インターンシップとは異なります。期間を定めた就業体験ではありません。
・企業様と大学生(講座受講生)が連携して、企業様から提示される課題の解決に取り組みます。
※その意味で、課題解決型学習(PBL〜Project Based Learning)の入門編と言えます。
(2)学生の活動には制約があることをご承知ください。
・本プログラムでの活動は、課外活動としての位置づけとなりますので、大学の授業、試験や公式行事などが優先されます。したがって、夏休み期間等を除き「平日の打ち合せ」などの日程調整は難しいと思いますので、ご了承ください。なお、オンラインミーティングの基本的なスキルは研修済みです。
・活動の進め方、日程の設定についてはチームメンバーと協議・調整していただくようお願いいたします。
(3)ミッションの設定について
・プログラムの中で学生に提示していただくミッションについては、受け入れ企業・団体様にて実際に解決・改善したい、知りたい課題をご提示ください。ただし、大学1回生によるチャレンジですので、難易度についてはご配慮ください。
・受け入れ企業・団体様とは事務局(生協職員と先輩サポーター)により、事前の打ち合わせをさせていただきます。ミッションの内容、提起の仕方についてご相談ください。
・受け入れにあたり、現場に来る前に知っておくべきこと、身につけておくべきことがある場合は事前講習などを実施しますので、お申し出ください。進め方・内容については、事務局にて協議・調整させていただきます。
(4)受入企業・団体様のメリット、費用等について
・大学生の社会的な体験を通じた成長機会をご提供にご協力ください。
・上記の趣旨より、大学生協より謝礼や費用のお支払いは致しませんのでご了承ください。
・受入いただくことで、大学生との接点がもてること、大学生の意識をつかんだり、学生視点の提言などを受けることができます。
(5)受講生の守秘義務等
・受講生およびサポーターの学生は、個人賠償責任保険の加入を義務付けています。
・受講生に対しては、当会より個人情報および企業機密の守秘義務がある旨指導を行います。
(6)その他
・参加した学生に対する言動が、ハラスメント行為とならないようご配慮ください。
・学生個人に対する謝礼・記念品の贈呈は、固くご辞退申し上げます。
以上
◆◆◆CP2 2024年度受入先アンケートから◆◆◆
Q:プログラム全体への評価をお聞かせください〜良かった点、評価できる点
・優秀な学生の方とのやりとりは刺激になりましたし、話をしていて面白いと感じる部分もありました。
・学生さんだけでなく、当社においても気づきが多い内容でした。
・毎年積極的な学生さんが多いですが、今年は例年に比べても全員が非常に積極的でスムーズに動けてよかったです。他社さんのチームの学生さんも面白いアイデアが多くて色々と発見がありました。
・他所から京都に来た若い学生さん、よそ者の若者ならではの、思い切りのよい取り組みができるところ
・自主的に参加するメンバーなのでポテンシャルが高い学生と課題に取り組むことができる。
・1回生のタイミングで、社会に実際に出て現場で学ぶプログラムが素敵だと思います。
・先輩サポーターの方もどうすればいいのかというところで一生懸命悩みながらも取り組んでくれていました。ミッションがスムーズにいかなかったことが、先輩サポーターの方にとっても非常に良い経験になったのではないでしょうか。
Q:もし、他の企業・団体へチャレンジプログラムの受入をお薦めしていただけるとしたら、どのような点が「推し」でしょうか?
・就活とはまた違った形で学生の方と交流できる。若い視点での考えを知ることができる
・一般的なインターンシップと異なり、FYPメンバーを経験したサポーターの存在
・単位のために大学が用意したプログラムやインターンに参加している学生と違い、こちらが追われるぐらいやる気と積極性に満ちている学生が多いので、企業としても刺激を得られて多くのことを学ばせてもらえる点
・よそ者の若者の素晴らしさ
・外から、学生から自分たちがどう見えているのかを客観視することができます。